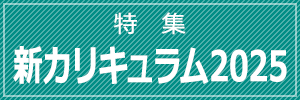就業体験講座前半を終えて

3回の職場見学は、なるべく多様性を持たせるために1次、2次、3次産業ベースで割り振ってあります。見学先は図らずも固定化しつつあり、今年は夏季休暇開始直後の8月2日に豊橋市役所と市議会、秋学期開始直前の9月14日に浜松の本田技研工業トランスミッション製造部を訪れました。例年通りですと、2月のイノチオグループの見学とレポートの発表会が続きます。
学生の6、7割がサービス業に就労する時代、見学先が実態に合わないのではないかという批判もありそうです。しかし、人の生活を直接支える農林水産業の重要性が無くなることがあるでしょうか。地産地消(フードマイレージ)や食料自給率を考えれば、むしろ活性化すべきでしょう。最近の農業は6次産業化――食料生産+食品加工+流通販売で1+2+3=6という訳です――を志向していますが、見学先はこの領域における先駆でもあります。
製造業で働く人はほぼ全ての先進国で減っていますが、これは必ずしも生産高の減少を意味しません。技術進歩と投資に伴い、機械が人間の労働を代替してきたのです。見学先では、シュシュとモーター音を響かせながら迅速に稼働する自動ロボットばかりではなく、人の組立て作業を支援する機械の働きも見ることができます。工場で人が不要になることはありませんし、消費財の製造部門は大規模なサービス部門と連動しています。
もうひとつ付け加えれば、かつて一部の社会学者や経済学者たちは、人間が労苦の多い肉体労働を離れ、有意な精神労働に携わるポストモダン(脱-近代)の時代が到来しつつあると論じました。残念ながら、現在のサービス業の労働環境は、必ずしもこの楽観論と一致しません。やりがいがあってストレスが少なく、体を動かすことが健康寿命を延ばす秘訣と聞けば、どういう就労形態が幸せに近いのか、判断が難しいところですね。
ひとつ嬉しい知らせがあります。この講座に参加した学生の一人が、かつての見学先に就職したのです。訪問先の変更が躊躇される理由のひとつなのですが、持続的で創造的、そして働く人を大切にしてくれる職場で働けるならば、われわれも素直におめでとうと言えるのだと思います。
(中野 聡)

就業体験講座・本田技研工業トランスミッション製造部(2018/09/14)