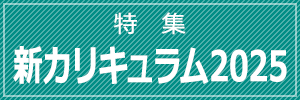教員からのメッセージ
年齢40歳は不惑と言いますが、60代になっても学ぶことの意味を考えています。若いころに考えた到達点と現実のギャップが気になる歳頃になったのかも知れません。でも、教育と研究の基本は、何歳になっても、いつの時代にも変わらないと思います。皆さんが大切に育むべきなのは、好奇心です。むろん、基礎的学力は必要なのですが、好奇心があってこそ正解を覚えるだけではない能動的な勉強が可能になります。自分で学ぶならば、大学時代になすべき本当の学修、つまり教養と自分だけの価値観を育み、高度な専門知識や技能を習得することも難しいとは感じないでしょう。
デカルトは、知ること、考えること、判断することが同様に大切であり、それらを人間の理性の働きとみなしていました。ならば、理性も好奇心の延長線上に生まれることになるし、逆にその意思がない人にこれこれを学べと強制するのは、本末転倒でもあります。わが国の教育は、この本末転倒の部分がやや過多なのかも知れませんね。またデカルトは、理性は全ての人間に平等に備わるものの、それを適切に使える人はほとんどいないとも考えていました。これから大学に入学される皆さんに期待したいのは、好奇心をもって自分の関心を探究すること、そして他者との係わりの中でそれを自分のものにすることです。それが、一生を通した学修の基礎になるのだと思います。
所属・職位・学位
豊橋創造大学経営学部・教授・Ph.D.(博士・社会史)
略歴
ウォーリック大学社会史研究所(英米比較労働史、イギリス社会史)など
所属学会
- 日本EU学会
- 社会政策学会
- 経済社会学会
- 西洋史学会
研究テーマ
EU(欧州連合)の社会政策および社会経済政策。特に、1980年代以降断続的に進行してきた先進社会経済体制のグローバルな自由主義化の潮流の中で、戦後体制の基幹的かつ民主主義的要素を維持・展開し、社会的に公正な秩序形成のあり方をEUと西欧諸国の現代史的経験の実証的、社会理論的考察を通して考えたい。他の先進資本主義諸国とわが国の社会経済システムには、基本的な差異と同時に数多くの類似点がある。直面する課題もしばしば近接している。こうしたコンテクストで欧州を学ぶ意味は、アメリカやイギリス社会の基調をなす自由主義思想(liberalism)、特に自由主義経済思想とは異なる論理によって構築される社会と経済のあり方を模索することにある。なお、フランス庭園史を含む西洋社会史にも関心を抱いている。
研究業績等(主なもの)
- 「労働市場の分断と社会的包摂―ポスト・ネオリベラル時代のEUと先進諸国におけるパートタイム規制の比較分析」豊橋創造大学紀要 第29号 2025年3月
- 「市場経済、戦後体制と市民社会の未来―EU社会対話の事例」日本EU学会年報 第43号 2023年5月
- 「ヨーロッパ2020戦略評価文書―EUの社会的側面をめぐって」豊橋創造大学紀要 第25号 2021年3月
- 「社会的パートナーシップ―EU資本主義モデルの挑戦と課題」日本評論社 2018年
- 「アクティブエイジング―豊かな高齢社会をめざして」豊橋短期大学紀要 第34号 2016年3月
- 「派遣労働―労働者保護と柔軟性と」ひろばユニオン 2015年11月
- ‘Maastricht Social Protocol Revisited: Origins of the European Industrial Relations System’, Journal of Common Market Studies 2014年9月.
- (研究ノート)「ドロール、社会プロトコルを語る」『豊橋創造大学紀要』第17号 2013年
- 「EUのフレクシキュリティ政策―社会的コンセンサスを求めて」社会政策学会編『社会政策』第3巻第2号 2011年
- 「EUの社会経済政策とリスボン戦略」高屋定美編『EU経済』ミネルヴァ書房 2010年収録
- ‘Managing European Works Councils from outside Europe’, in Ian Fitzgerald and John Stirling ed. (2004) European Works Councils: Pessimism of the Intellect, Optimism of the Will? London: Routledge.
- 『EU社会政策と市場経済-域内企業における情報・協議制度の形成』創土社 2002年
教育関連業績等(主なもの)
- 「西洋経済史・社会史卒業論文集」 … 卒業論文の要約集で、平成12(2000)年4月以来継続中。
- 「EUの労働時間と非典型雇用規制」… 高校生向けの欧州連合駐日代表部メールマガジンEU-MAG記事(2013年5月)。
担当科目
- 入門ゼミナール
- 基礎ゼミナール
- 西洋経済史
- 社会学入門
- 現代ヨーロッパ経済論
- 専門ゼミナール
- 社会政策と市場経済
- など
ゼミナール研究テーマ
現代社会論および社会経済史に関連するテキストの輪読と学生が各自のテーマで作成する論文から構成する。近年輪読に利用したテキストは、吉見俊哉『ポスト戦後社会』岩波新書2009年、橘木俊詔『格差社会』岩波新書2006年、阿部彩『子どもの貧困』岩波新書 2014年、G.エスピン-アンデルセン『福祉資本主義の3つの世界』ミネルヴァ書房 2001年、宮本太郎『生活保障』岩波新書 2009年、猪木 武徳『戦後世界経済史―自由と平等の視点から』中公新書 2009年、藤井 威『福祉国家実現へ向けての戦略―高福祉高負担がもたらす明るい未来』ミネルヴァ書房 2011年など。
学外講義テーマ
- 大学で経済・経営学系を学ぶ
- 大学で社会科学を学ぶ
- 欧州統合の現在と未来